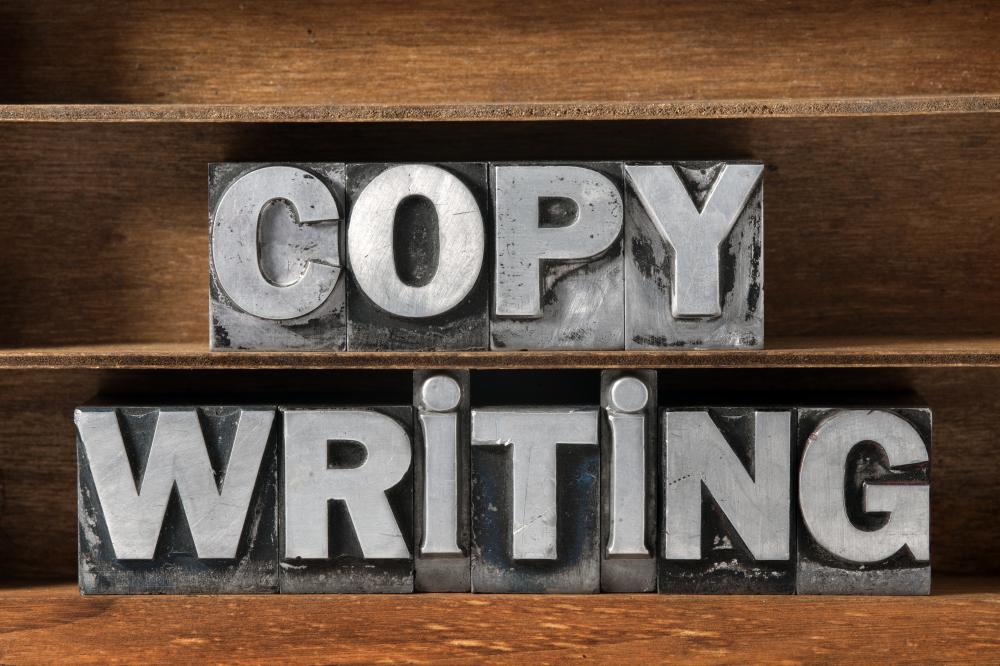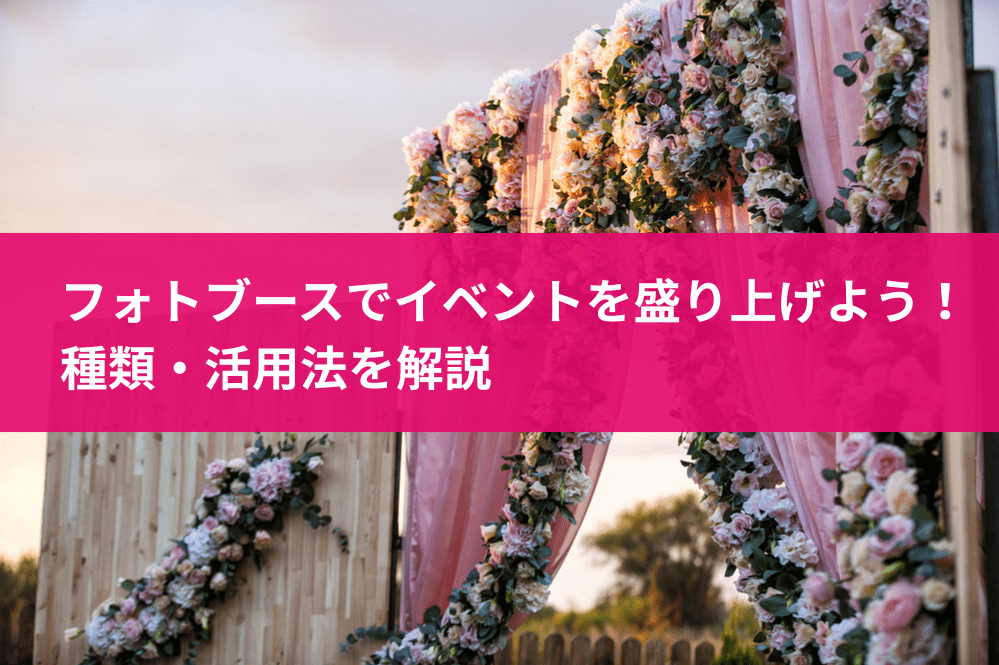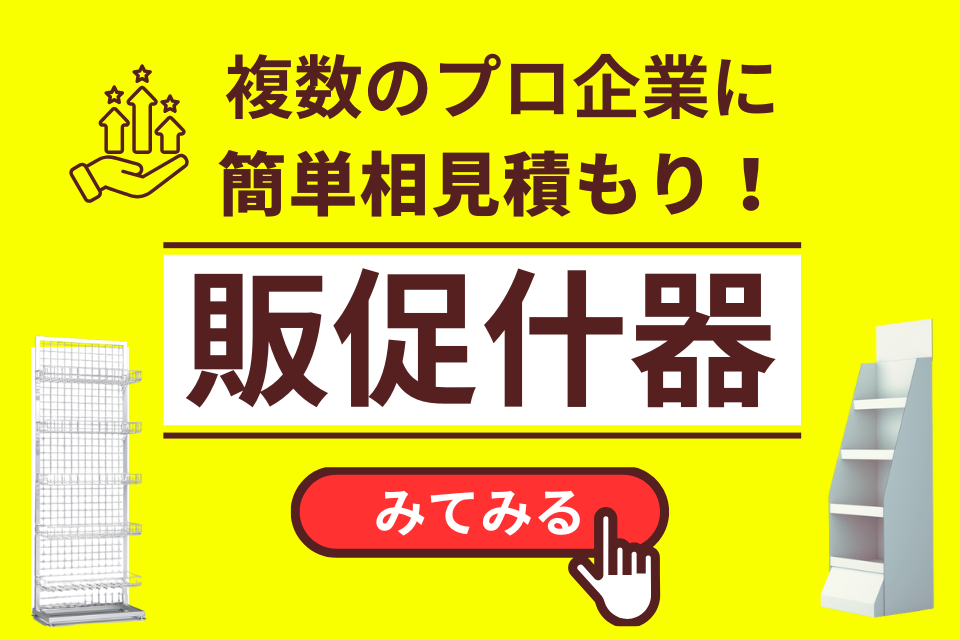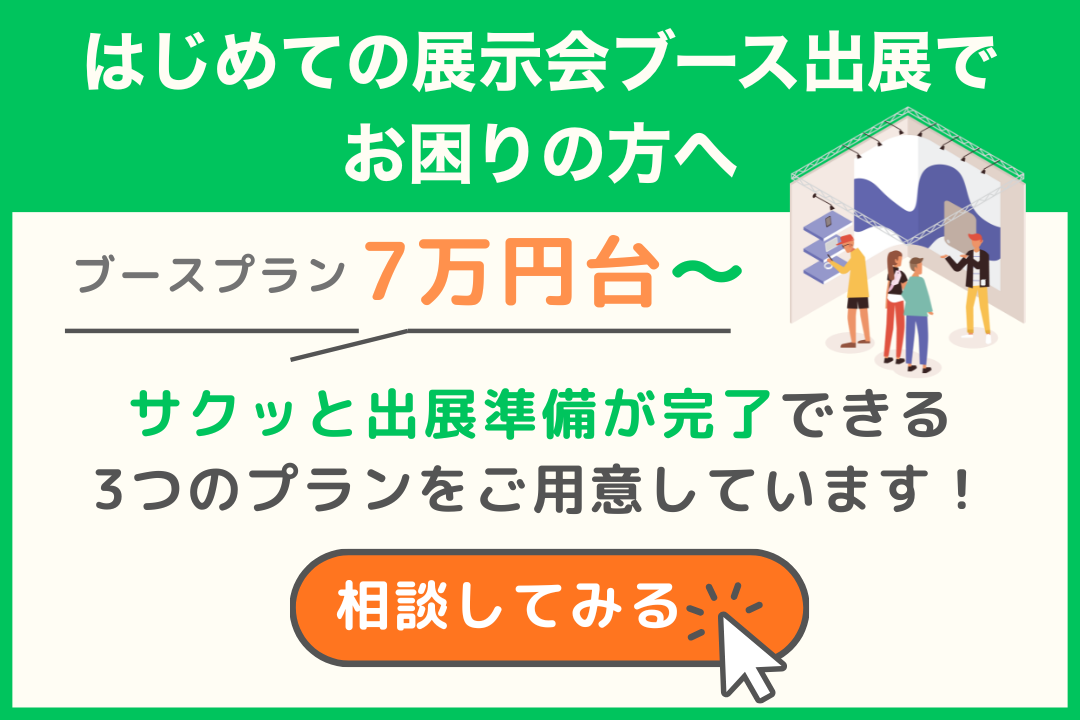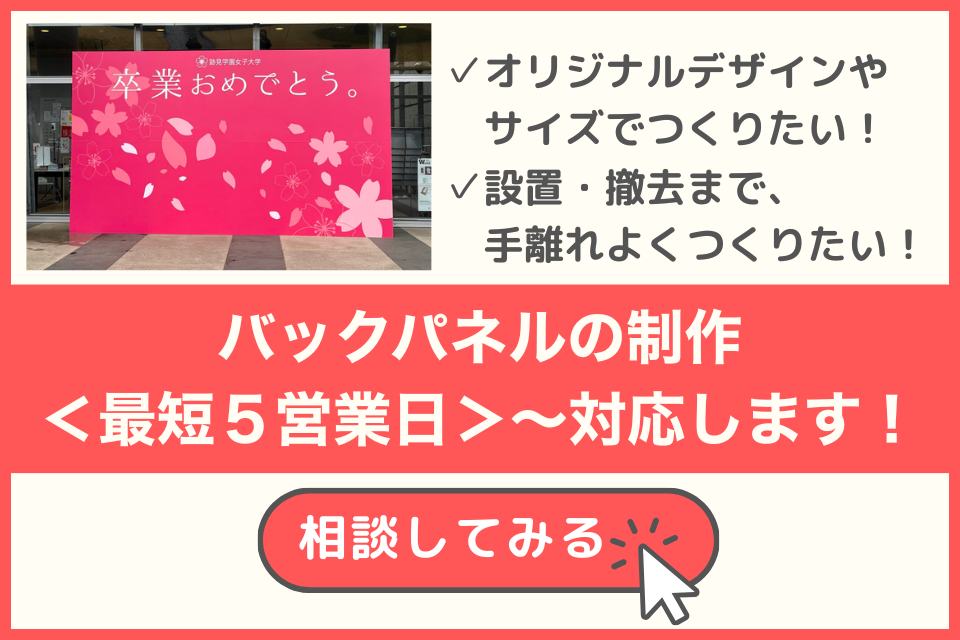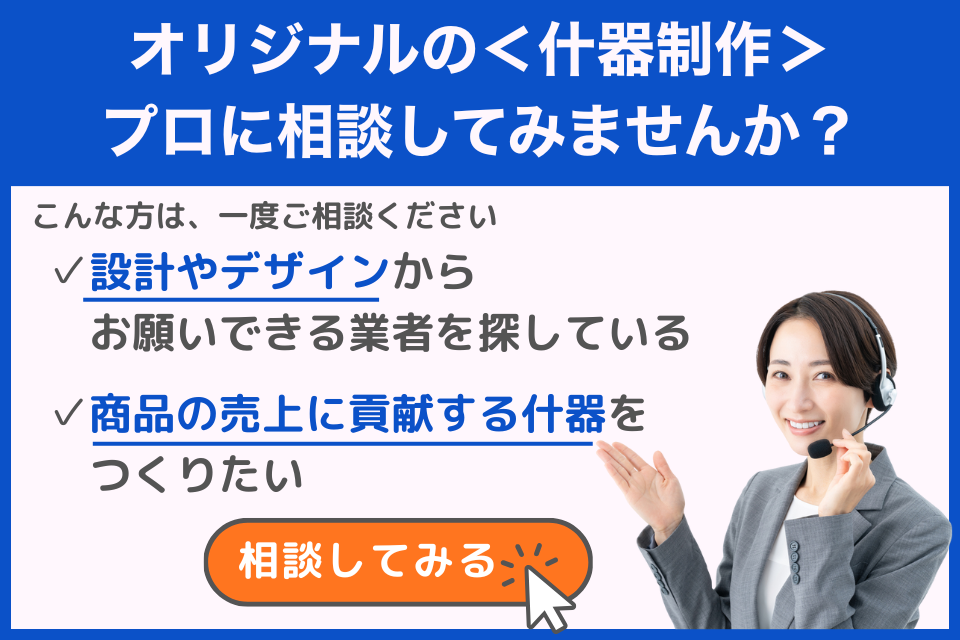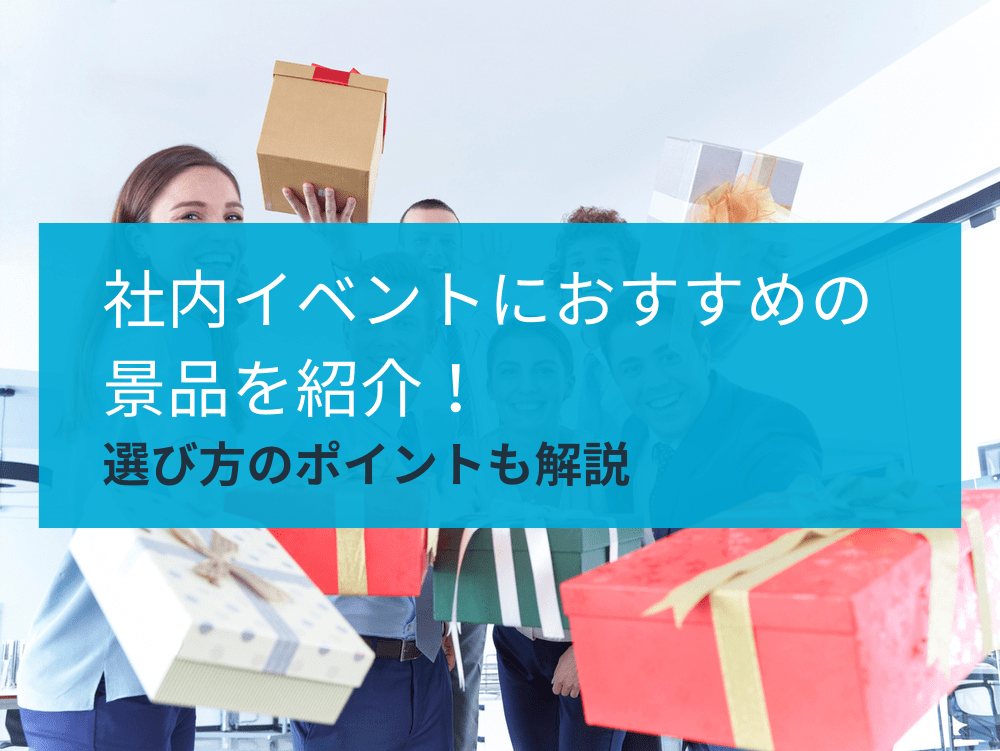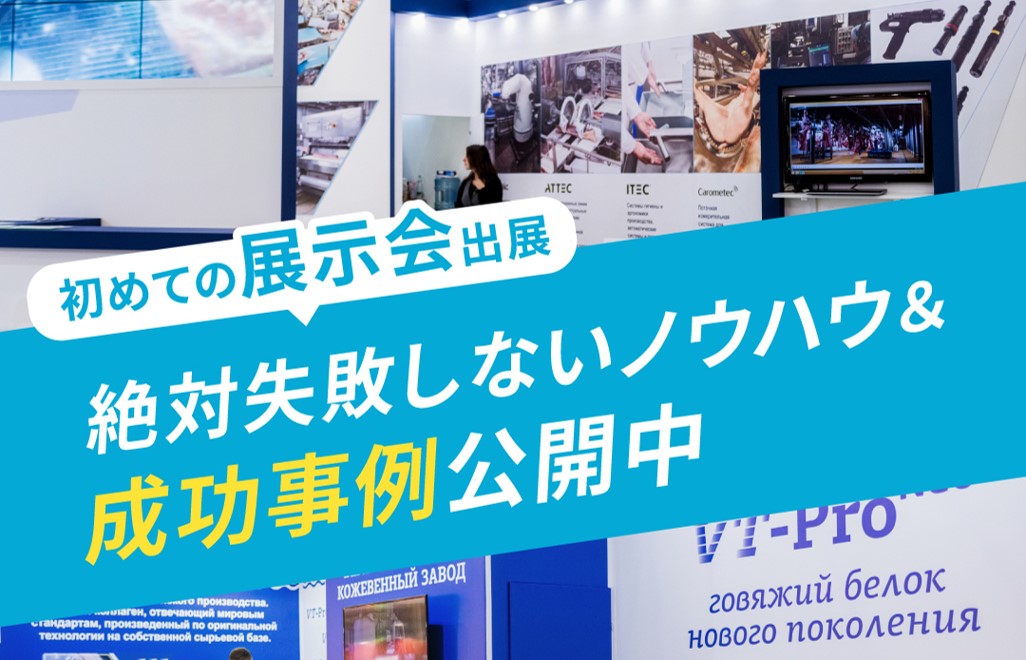- 展示会ノウハウ
【テンプレートあり】展示会の企画書の作り方|企画を通す3つのポイントも解説
公開日 2025.04.24 /更新日 2025.10.23

Contents
【テンプレート】展示会の企画書のフォーマット
展示会の企画書の基本的なフォーマットは上記のとおりで、以下をコピーして使えます。
なお、上記はあくまで一例なので足りない項目があれば追記が必要です。
社内に決められたフォーマットがあるなら、そちらに従いましょう。
次章から企画書の作成方法を解説します。
展示会の企画書の作成方法6ステップ
展示会の企画書は以下の6ステップに沿って作成を進めます。
展示会の企画書の作成方法6ステップ
|
順に見ていきましょう。
1.「出展の目的・ターゲット・出展する展示会」を定める
まずは、出展の目的とターゲットを明確にします。
目的とターゲットが明らかになれば、自社に合った展示会を選びやすくなります。
なお、企業が展示会に出展するときの目的は、主に以下のとおりです。
- ・新規顧客の獲得
- ・商品やサービス、自社の認知度アップ
- ・既存顧客との関係の強化
目的が定まったら、ターゲットも設定します。
例えば、電子機器メーカーが新規顧客の獲得を目的とし、「自社で取引が少ない教育業界の顧客(私立高校を運営する学校法人など)」をターゲットに定めたとします。
その場合、教育関係やDX関連の展示会が出展先の候補です。
目的とターゲットを最初に定めると出展すべき展示会がわかり、ほかの項目も決めやすくなります。
2.「KPI」を設定する
1つ目のステップで定めた目的やターゲットに合わせて、KPI(数値目標)も設定します。
KPIを設定すると「出展準備や当日の運営で何を指標にして動けばいいか」が明確になるためです。
ただし、展示会のKPIとして売上を設定するのはおすすめできません。
単価の低い商品を展示会で直接販売している場合は、売上額をKPIにするのも1つの方法ですが、展示会は商談までで終わるケースがあるためです。
また、情報収集を目的に訪れている来場者が多い展示会では、商談にすらつながらない場合もあります。
そのため、名刺獲得数や商談件数などをKPIに設定するのがおすすめです。
1つ目のステップと同じ例で、電子機器メーカーが新規顧客を獲得したい場合は「名刺50枚獲得」のようなKPIを定めましょう。
明確なKPIがあれば、出展後の効果測定も実施しやすくなります。
3.「コンセプト」を決める
展示会の企画書を作成するときは「誰に・何を・どのように」伝えるかの軸である、コンセプトも決めます。
コンセプトを定めないと、販促物を作成したり集客方法を決めたりする際に、方針がぶれてしまうためです。
具体的な例としては「私立高の校長先生に導入を検討してもらえるよう、勉強がはかどるうえ、リーズナブルな高校生向け学習タブレットがあると伝える」といったものです。
ステップ1でターゲットはすでに決まっているため、以下の流れでコンセプトを定めていきましょう。
| No. | 手順 | 例 |
| 1 | 商材が複数ある場合、アピールする商材を選ぶ | 電子機器メーカーの場合「高校生向けの学習タブレット」など |
| 2 | ターゲットのニーズや悩みを調べる | ターゲットが私立高校を運営する学校法人の場合「授業にタブレット端末を導入したいが、できるだけ予算を抑えたい」など |
| 3 | キャッチコピーを決める | タブレット端末を訴求する場合「価格は下げて学習効果アップ」など |
コンセプトが決まると、ブースのデザインを決めるうえで重要な要素であるキャッチコピーもスムーズに決まります。
なお、キャッチコピーの作り方は以下の記事で紹介しているため、あわせてご覧ください。
4.出展日に合わせて「スケジュール」を立てる
出展日から逆算して、以下のように「いつ・何をするか」をスケジュールとして決めることも重要です。
| いつ | 何をするか |
| 3ヵ月前 | ・出展の企画 ・販促物やブース制作の外注 ・集客方法の決定 |
| 1ヵ月前 | ・SNSやWebサイトで出展を告知 ・招待メールや招待状の送付 ・スタッフの手配 ・ブース運営スタッフのマニュアル作成 |
| 1週間前 | ・見込み顧客へのリマインド ・マニュアルの読み合わせや最終チェック ・会場でのブース設営 |
特に、ブースや販促物の作成などの外注を検討している場合は、早めの相談がおすすめです。
ブースや販促物の作成は、事前のヒアリング・デザイン制作や修正・印刷会社への発注など複数の工程に分かれているため、対応に時間がかかります。
直前に相談すると、引き受けてもらえない恐れもあるので注意が必要です。
なお、展示会パッケージ「はじめての展示会」や「スグラク展示会」なら、複数の工程に分かれている作業もワンストップで対応します。
一方で、招待メールの送信や出展の告知は展示会の約1ヵ月前と、リマインドとして1週間前に実施するのがベストです。
あまりに早すぎると見込み顧客から忘れられてしまい、遅すぎるとすでに別の予定で埋まっている場合があります。
準備は基本早めに進めるのがおすすめですが、招待や告知に限ってはタイミングを見計らいましょう。
5.「ブース」のデザインや制作物・集客方法を決める
ブースのデザインや、販促物など出展にあたって制作するもの、集客方法も決めていきます。
ブースや販促物については、外注する際のヒアリングで「どのようなブースや販促物にしたいか」を聞かれるため、企画の段階で方針を決めるのがおすすめです。
3つ目のステップで決めたコンセプトを共有すると、ターゲットや訴求する商品がわかるので、外注先から一貫性のある提案をしてもらえます。
例えば、新規顧客を獲得したい場合、考えられるブースや販促物は以下のとおりです。
- ・ブース:入り口を広くした立ち寄りやすいブース
- ・販促物:訴求する商品を載せたチラシやパンフレット、名刺交換を促すノベルティなど
また、展示会に出展するだけでは十分な集客が見込めない場合もあるため、集客方法も考えます。
メールや招待状・SNS・Webサイトでの告知など、自社が活用できる手段を使って、できるだけ多くの人に出展する旨を伝えましょう。
集客効果を高めるには、展示会の1ヵ月前と1週間前など、リマインダーとして何回かに分けて告知するのがおすすめです。
なお、メールを送るなら以下の記事もあわせてご覧ください。
6.「予算」を決定する
集客方法まで決まったら予算を策定します。
展示会の出展にはさまざまな費用がかかるため、事前に予算をどのように使うか計画を立てましょう。
予算の内訳は主に以下のとおりです。
- ・出展料
- ・ブースデザイン費や製作費
- ・販促物などの製作費
- ・スタッフの人件費
- ・資材などの運搬費
ただし、上記はあくまで一般的な費用です。
不要な費用や他に必要なものが発生する場合もあるため、自社のケースに当てはめて調整しましょう。
例えば、社員で当日のブース運営をする場合、スタッフの人件費は不要です。
なお、展示会の費用に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、ご一読ください。
展示会の企画書を通すための3つのポイント
展示会の企画書を通すには、以下のポイントを押さえます。
展示会の企画書を通すための3つのポイント
|
順に見ていきましょう。
1.客観的なデータや資料を提示する
展示会の企画書では、客観的なデータや資料を提示すると、説得力を高められます。
「私は○○だと思います」のような主観では根拠が不足してしまうため、データや資料で補足が必要です。
例えば、今まで出展した経験がない展示会に出展したい場合、その展示会の過去の開催データや自社の実績などを活用します。
データや実績をもとに、以下のように展示会の来場者数や客層、想定売上などを示しましょう。
| No. | 手順 | 例 |
| 1 | まずは過去実績から、今回の来場者数や客層を把握する | ・来場者数:想定20,000名 ・客層:経営層や管理職の割合が40% |
| 2 | 過去に出展した同じような規模の展示会での実績や、名刺交換した人の割合などから、想定リード獲得数を出す | ・ブース訪問数:100件 ・リード獲得数:10件 (訪問100件×リード転換率10%) |
| 3 | 商談化率の過去の実績を参考に、想定商談数を出す | 商談数:5件 (商談化率50%) |
| 4 | 商談後の成約率をもとに、成約数を出す | 成約数:2件 (成約率40%) |
| 5 | 成約数と1顧客あたりの平均売上をもとに、想定売上を出す | 想定売上:60万円 (成約2件×単価30万円の場合) |
「自社製品のターゲット層とマッチしているか」「どのような成果が見込めるか」などを客観的に説明し、出展する意義を示せます。
データや資料を用いて、決裁者が納得できる企画書を作りましょう。
2.予算の使い道を明らかにする
予算の使い道を明記することも企画書を通すためのポイントです。
特に、予算を交渉したい場合は、何にどのくらい予算を使うかを明らかにする必要があります。
会社の資金を使って展示会に参加する以上、予算の使い道がわからないと決裁者に納得してもらえません。
また、今回の承認が得られないだけではなく、次回以降の出展にも予算を割いてもらえない恐れがあります。
予算は項目別で記載し、可能であればどのような効果が得られそうかもデータを添えて、以下のように記載しましょう。
- ・出展料:20万円
- ・ブース設営費:25万円
- ・販促物の製作費:40万円(※)
(※)昨年チラシの作成枚数を200枚増やしたところ、ブースへの来場人数が30%ほど増加したため、今回も枚数を増やす想定
使い道や効果を示すと、予算の交渉もスムーズです。
3.過去の失敗事例を把握する
過去に自社が展示会へ出展した経験があるなら、当時の担当者に話を聞いたり企画書に目を通したりしましょう。
外注先にも話を聞くと、他社が出展したときのエピソードを聞ける可能性もあります。
特に失敗事例を把握するのがおすすめです。
以下のような過去の失敗を事前に知っておくと、同じような失敗を避けられます。
- ・「ブースの発注が遅れて出展に間に合わなさそうだった」
- ・「運営スタッフの人数が多すぎて予算を超えそうだった」
自社における過去の失敗や他社の事例も聞いておくと、企画書を提出する前に同じ失敗をする恐れがないかをチェックできます。
企画書に沿って展示会の準備を進めるなら「はじめての展示会」
企画書が通ったら出展の準備を進めていきますが、準備が企画書のとおりに進むか不安なら、展示会パッケージ「はじめての展示会」がおすすめです。
3つのパックから予算に合わせてプランを選ぶだけなので、予算オーバーが起こりにくく、スケジュールが押していても出展準備がすぐに完了します。
さらに、アイテムの追加や変更もできるので、企画書に記載したターゲットやコンセプトに沿って、自社に合ったツールや販促物のご提案・手配も可能です。
レンタル品の手配や、オプションとして施工・撤収などもまとめて依頼できるため、準備がスムーズに進められます。
企画書を作成したものの、ブースの準備をどのように進めればいいか悩んでいるなら、以下より無料でお問い合わせください。
企画書を練って展示会を成功させよう
企画書を作成するときの基本的なステップは以下のとおりです。
展示会の企画書の作成方法6ステップ
|
なお、企画書を通すためには、客観的なデータの提示や予算の明確化、失敗事例の把握がポイントです。
企画書を作りこんで決裁者を納得させ、展示会を成功させましょう。
もし、企画書に記載したとおりにブース製作や当日の運営ができるか不安なら「展示会マスター」の利用がおすすめです。
ブースづくりや集客に必要なスタッフの手配など、準備から当日の運営までをワンストップでサポートします。
「ブース製作の進め方がわからない」「スタッフの人数が足りない」といった課題をヒアリングしたうえでサービスを提案しますので、以下より気軽にお問い合わせください。
この記事に関するタグ