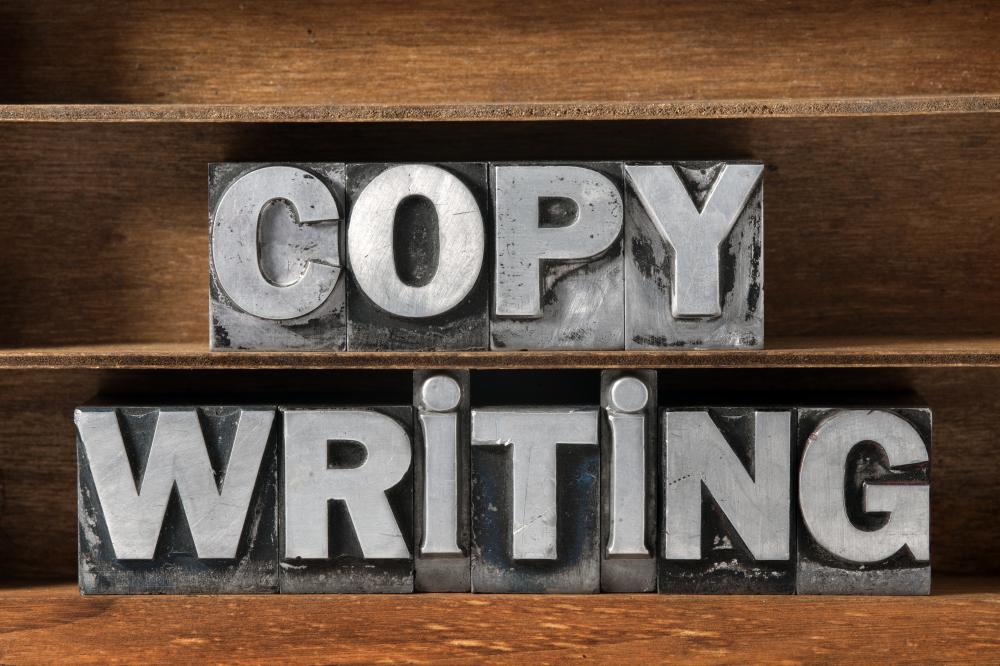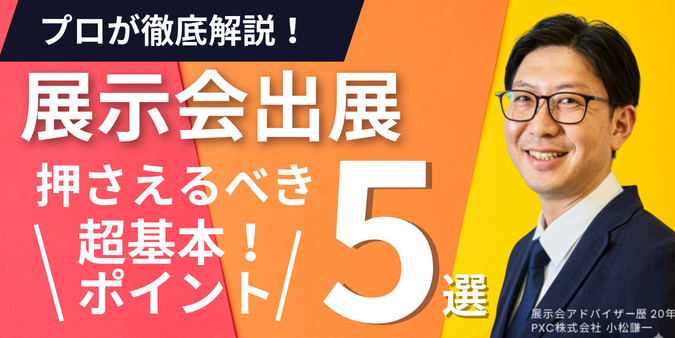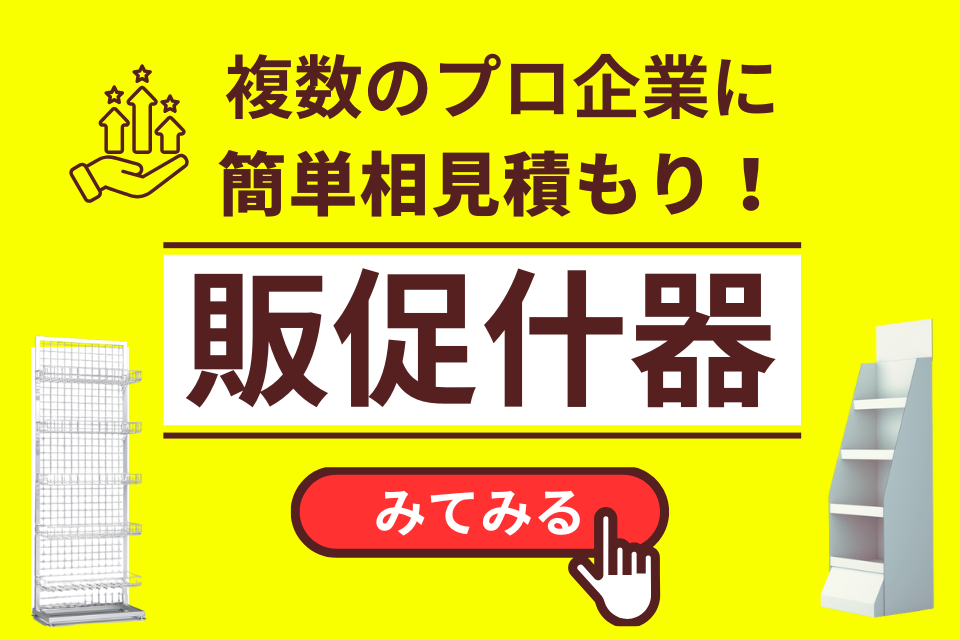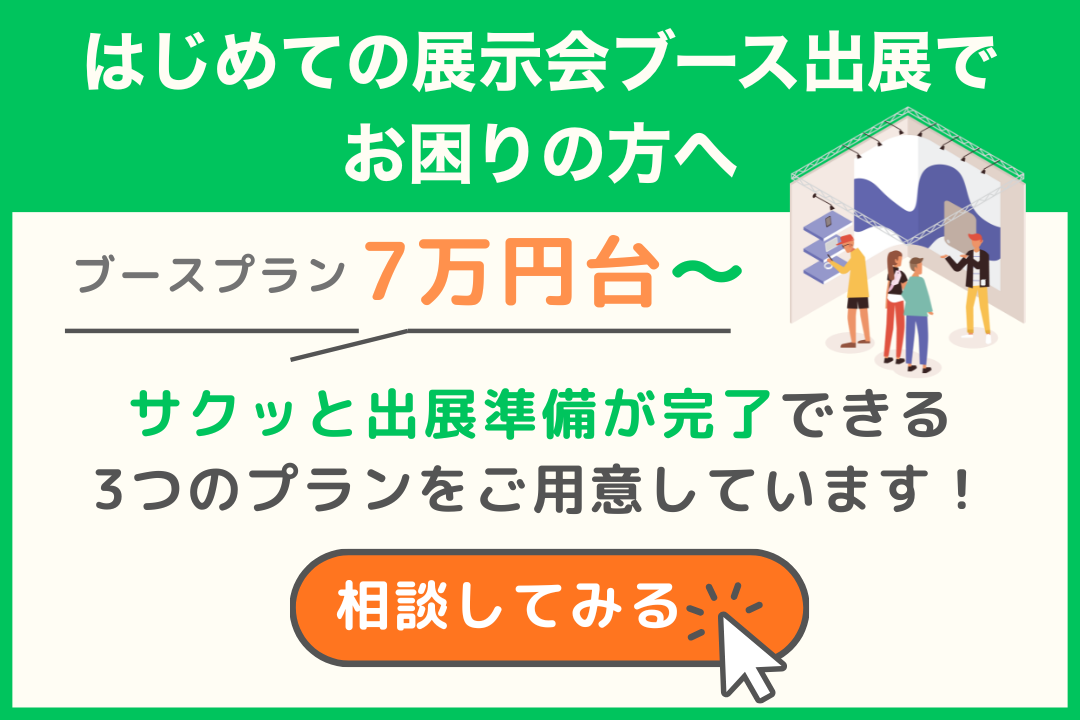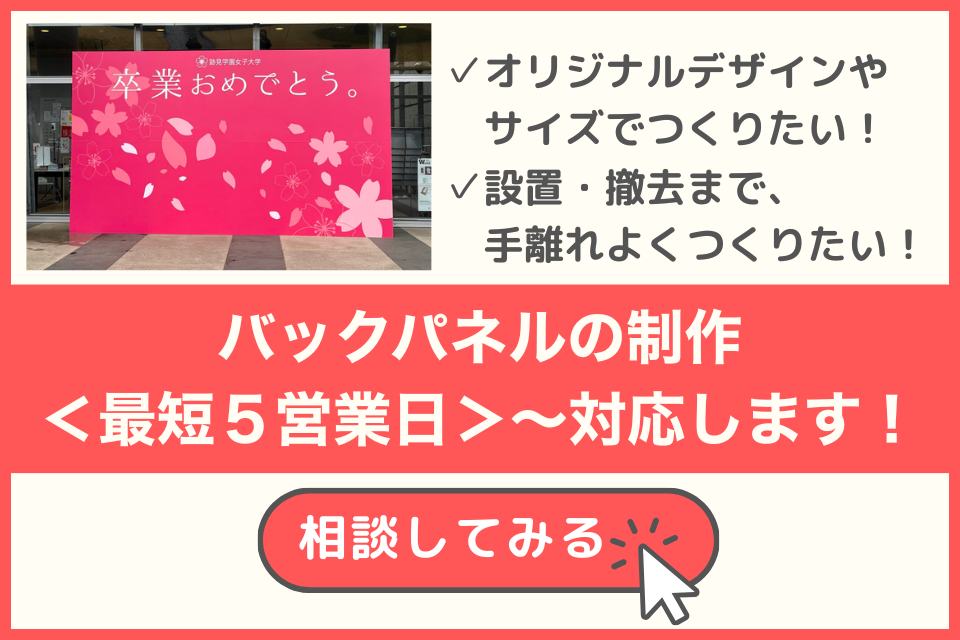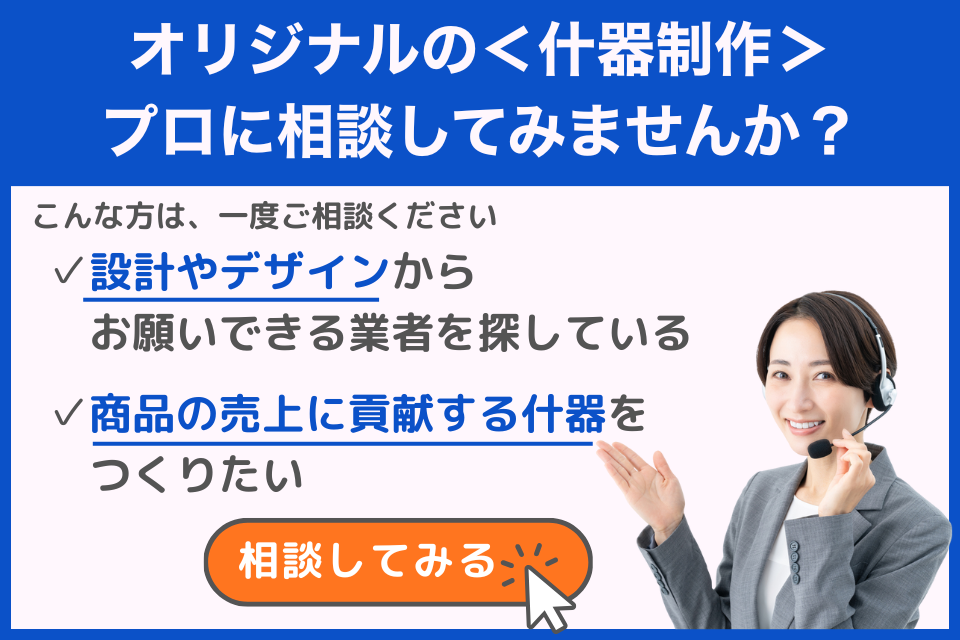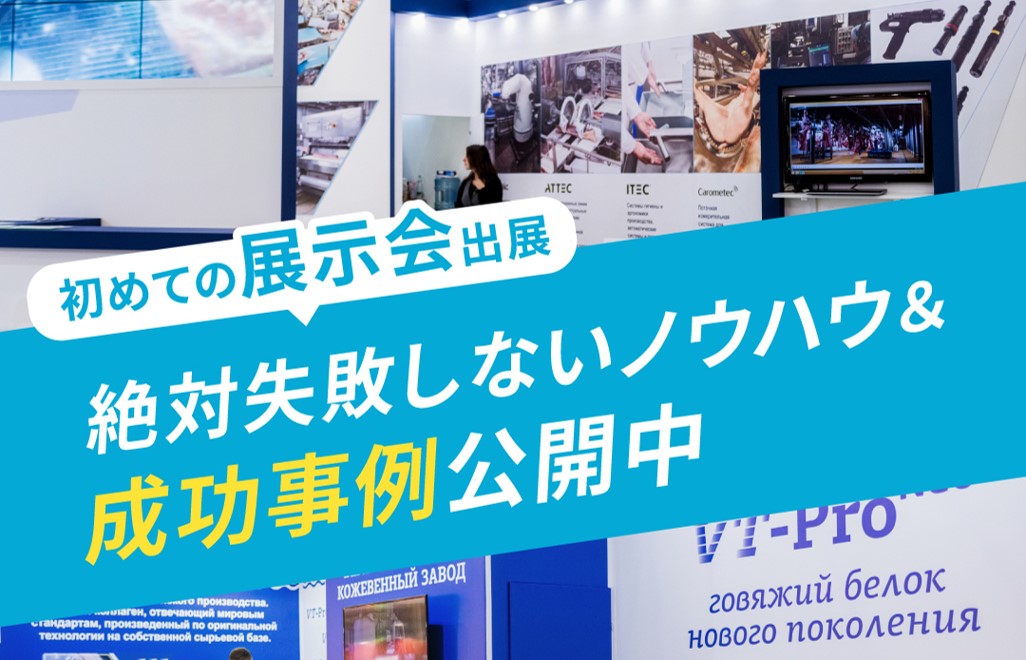- 展示会ノウハウ
展示会のプレゼン準備6ステップ|資料作成のコツなど成功ポイントを解説
公開日 2025.08.28 /更新日 2025.10.23

Contents
展示会でおこなうプレゼンの準備6ステップ
展示会でプレゼンをおこなう際は、以下のステップで準備を進めます。
展示会でおこなうプレゼンの準備6ステップ
|
順に見ていきましょう。
1.目的とターゲットを決める
展示会でプレゼンをおこなう際は、まず出展の目的とターゲットを決めます。
目的やターゲットを決めずにプレゼンの内容を決めても、情報量が多すぎたり、まとまりのない内容になってしまったりするためです。
目的やターゲットが決まっていれば、プレゼンの大枠や方向性なども決めやすくなります。
例えば、目的がブランドや商品の認知度アップなら、業界の著名人を招いてプレゼンをおこなう、といった大枠が決まります。
「誰に・何を伝えるプレゼンにするか」を具体的に設定すると、聴き手に刺さる情報を提供できるプレゼンの実施が可能です。
2.キーとなるメッセージを一文で作る
来場者に「これだけは覚えて帰ってほしい」という核となるメッセージを、一文でまとめます。
展示会には競合他社が出展するため、簡潔なメッセージで来場者の記憶に自社の印象を残すことが必要です。
例えば、電子契約システムを扱う企業なら「契約書を電子化させて業務をラクに」といったように、自社の商品がもたらす価値やメリットを伝えましょう。
メッセージだけでは商品の説明として不十分なので、詳しい説明はプレゼン内で補足します。
なお、キャッチコピーを作りたい場合は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
3.プレゼンの資料を作成する
目的・ターゲット・メッセージなどが決まったら、PowerPointやGoogleスライドなどを使って、ベースとなる資料を作成します。
プレゼンで話す内容を補足し、聴き手の理解を深め、説明をよりわかりやすく伝えるためです。
プレゼンの大枠を考える際には、PREP法に沿った構成の作成をおすすめします。
「PREP」は、以下の頭文字です。
- ・Point(結論)
- ・Reason(理由)
- ・Example(具体例)
- ・Point(結論)
上記の順番どおり結論から話し始めると、聴き手が「結局何が言いたいのか?」と迷うのを防ぎ、話の内容を理解しやすくなります。
スライドを作成するときの具体的なコツは、後述する「展示会用のプレゼン資料を作成するコツ」で詳しく解説します。
4.デモや備品の準備をする
プレゼンでデモンストレーションを実施する場合は、デモの手順をチェックします。
当日のデモをスムーズにおこない、万が一トラブルが発生しても冷静に対処するためにも、商品の操作方法をあらためて確認するのがおすすめです。
また、デモで使う以下の備品なども用意します。
- ・デモの手順書
- ・必要なケーブル類
- ・予備機
- ・録画デモ(機器が作動しないときのため)
不測の事態が発生しても慌てずに対応するため、予備機や録画デモも準備しておくと安心です。
5.リハーサルを繰り返しおこなう
プレゼンの内容が固まったら、通しでリハーサルを複数回おこないます。
改善点を見つけ、本番で落ち着いて話せるよう、リハーサルは繰り返し実施しましょう。
リハーサル中は時間を計りながらビデオなどで録画をして、話すスピードや声の大きさ、わかりにくい点がないかを確認します。
また、身近な人にプレゼンを見てもらい、客観的な意見やアドバイスをもらうことも重要です。
自分では気付かない、話し方の癖や改善点が見つかる場合があります。
アドバイスをもとに、プレゼンの質を高めて本番に臨みましょう。
6.当日に最終確認をする
展示会当日、会場に到着したら、プレゼンを開始する前に以下の最終チェックをおこないましょう。
- ・機材がそろっているか
- ・マイクの音量は適切か
- ・スライドを映すプロジェクターや画面は問題なく映るか
- ・想定していたとおりの動線で動けそうか
また、プレゼンをおこなうステージやブース内で、想定どおりの動線で動けそうかどうかも確認しましょう。
可能であれば、会場でも本番と同じ環境で一度リハーサルを実施するのがおすすめです。
実際の声の通り方やスライドの見え方などを確かめられるので、より安心して本番を迎えられます。
展示会用のプレゼン資料を作成するコツ
展示会のプレゼンで使う資料を作成するときのコツは、以下のとおりです。
展示会用のプレゼン資料を作成するコツ
|
順に解説します。
1.スライド1枚につきメッセージを1つに絞る
プレゼンでは、スライド1枚につき、伝えるメッセージを1つに絞ります。
1枚のスライドにさまざまな情報が詰め込まれていると、要点がわからなくなってしまうためです。
細かい情報まですべてをスライドに記載する必要はありません。
スライドはあくまで重要なポイントだけをまとめ、詳細は口頭で説明すると、メッセージをより明確にできます。
また、スライドの文字は大きくして、ブースから離れた聴き手にも見えるように整えるのがおすすめです。
1枚のスライドで伝える内容は1つに絞り、別の内容に触れる際は、新しいスライドを作成しましょう。
2.図・写真・動画を取り入れる
資料には、図や写真、動画を取り入れるのもコツの1つです。
文字だけのスライドは単調な印象になってしまい、聴き手を飽きさせる恐れがあります。
場合によっては、図などがなく言葉だけの説明だと、情報がうまく伝わりません。
例えば、商品の図面や使用中の写真、操作方法を説明する動画などを使うと、聴き手は使用シーンをイメージしやすくなります。
図や写真などをスライドに盛り込み、商品の魅力を直感的に伝えましょう。
3.冒頭のフックを強くする
プレゼンの冒頭では、聴き手の心をつかむ「フック」を作るのがおすすめです。
聴き手の全員が、自社のプレゼンに強い関心を持っているとは限りません。
そのため、開始早々に聴き手の興味を引き、最後まで聞いてもらうための仕掛けが必要です。
例えば、以下のように聴き手が驚いたり、相手にメリットがある内容で話を始めたりします。
- ・「ペーパーレス化を進めると、年間○○万円のコスト削減が可能です」
- ・「○○を使うと、作業時間を3分の1に短縮できます」
冒頭で驚く内容やメリットを提示し「さらに情報を知りたい」と感じさせると、話に聴き入ってもらえる可能性が高まります。
4.聴き手が参加できる仕掛けを作る
ただプレゼンを聴いているだけではなく、聴き手が参加できるような仕掛けを盛り込みましょう。
話を聴いているだけでは聴き手の集中が途切れてしまいますが、参加を促すとプレゼンに意識を向けてもらいやすくなります。
聴き手が参加できる仕掛けの一例としては、以下のとおりです。
- ・業界や自社の商品にまつわるクイズを出す
- ・聴き手の業界をたずねて挙手を促す
- ・デモを体験してもらう
ただ聴いているだけのプレゼンよりも、聴き手の記憶に残る効果が期待できます。
展示会でプレゼンを進行するときのポイント
プレゼンを進行する際は、以下のポイントに気を付けます。
展示会でプレゼンを進行するときのポイント
|
順に見ていきましょう。
1.大きな声でゆっくり抑揚をつけて話す
展示会でのプレゼンは、大きな声でゆっくりと抑揚をつけて話すのがポイントです。
声が小さかったり、話すスピードが速すぎたりすると、内容が聞き取れない場合があります。
また、一定のトーンで話すよりも、抑揚をつけると聴き手に共感や感情移入してもらいやすくなります。
ちょうど良い話し方がわからない場合、以下のように話すのがおすすめです。
| 項目 | 話し方 |
| 声の大きさ | 会場の一番後ろにいる聴き手よりも、さらに一列後ろへ声を届けるイメージで話す |
| 話すスピード | 10秒で50~60字を話す |
| 抑揚 | 重要な箇所を強調する際は、声を少し高くする |
リハーサルをおこなう際は、プレゼンの内容だけではなく、上記の項目に関してもアドバイスを受けましょう。
2.アイコンタクトを分散させる
来場者の席をいくつかのブロックに分け、順にアイコンタクトを送ることも重要です。
「自分たちに向けて話している」と聴き手が感じれば、注意して話を聴いてもらいやすくなります。
原稿を読み上げるプレゼンになっていないか、身体がスライドのほうだけを向いていないか、同僚などに確認してもらいましょう。
原稿は補助に留めて顔を上げるようにし、身体は来場者の席へ向けます。
聴き手の目を見て話すのがベストですが、緊張するなら会場の四隅を見るように視線を動かすのも、1つの方法です。
3.専門用語や難しい言葉は補足をする
展示会のプレゼンでは、専門用語や固有名詞など、難しい言葉には補足を付けるのがおすすめです。
なかには、業界に詳しくない方や専門用語を初めて耳にする方が、プレゼンを聴いている場合もあります。
そのため、専門用語や固有名詞を使うときは、以下のようにかみ砕いて一言で説明しましょう。
- ・「EOSとはIT業界で『サービス終了』を意味します」
- ・「当社が独自に開発した○○(商品名)」
言葉の意味がわからないままだと、聴き手としては気になるうえに、話についていけなくなる恐れもあります。
また、耳で聞いた言葉を正確に認識してもらうため、スライドには専門用語や商品名を記載するのも重要です。
4.質問はまず受け止めて簡潔に回答する
質問が出た場合、会場全体に聞こえるよう質問内容を繰り返して確認し、要点だけを答えます。
質問に対する詳しい話は、プレゼン後の名刺交換や個別相談の時間に回すと、予定していた時間どおりに進行しやすくなります。
なお、想定される質問を事前にリストアップし、回答を準備しておくのも重要です。
また、リハーサルでも質疑応答をおこなうと本番でも慌てずに済むので、練習しておきましょう。
展示会のプレゼンに集客するなら「展示会マスター」
ここまでプレゼンの準備方法やコツなどをお伝えしましたが、内容が素晴らしくても聴き手がいなければ、新規顧客の獲得など狙った目的を達成できません。
もし展示会のプレゼン集客にお悩みなら、展示会の出展サービス「展示会マスター」がおすすめです。
展示会マスターは、集客の課題を解決する、幅広いサービスを提供しています。
スタッフの手配が可能なので、自社ブースへ集客する人員が足りなくてもリソースの追加が可能です。
また、プレゼン内に動画を取り入れたくても制作方法がわからなかったり、時間がなかったりする場合でも、制作を依頼できます。
ブースやチラシ、パンフレットなどの製作もプロに相談できるので、集客に悩んでいる場合は以下よりお気軽に問い合わせください。
展示会のプレゼンを成功させよう
展示会でプレゼンを実施する際は、目的やターゲットを決めたうえで資料を作成し、繰り返しリハーサルをおこないます。
資料の作成時には1スライドにメッセージは1つ、プレゼンの進行には大きな声でゆっくり話すといった点がポイントです。
準備の進め方やポイントを把握し、当日のプレゼンを成功させましょう。
もし、プレゼンの準備やブース製作にお悩みの場合は、展示会の出展サービス「展示会マスター」がおすすめです。
プレゼン内で使う動画の制作をはじめ、ブースづくりや集客につながるノベルティの作成など、展示会に必要なサービスがそろっています。
プレゼンに必要なアイテムや各社の課題に合わせて最適なサービスを提案しますので、まずは以下よりお気軽に問い合わせください。
この記事に関するタグ