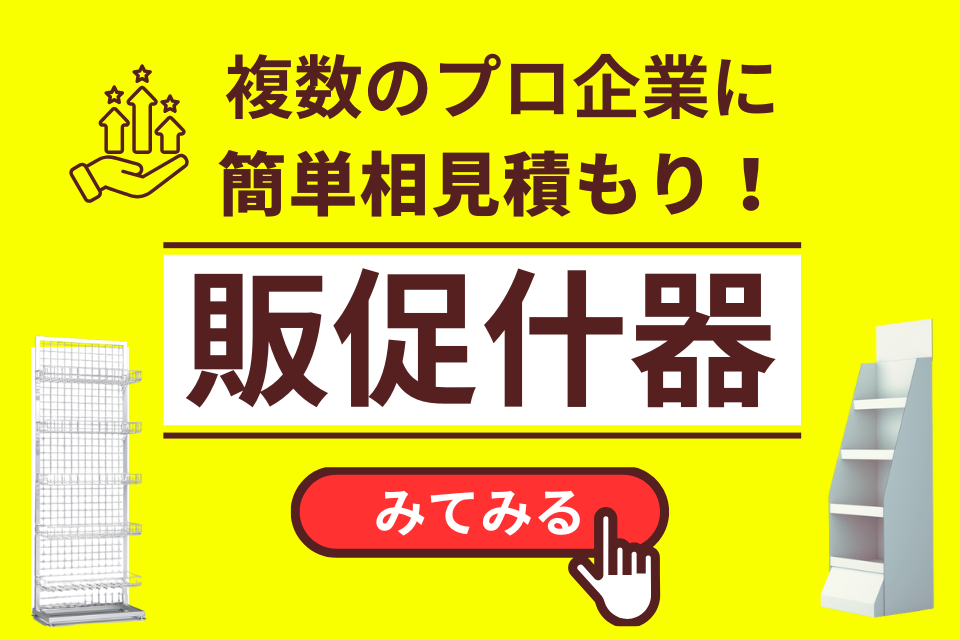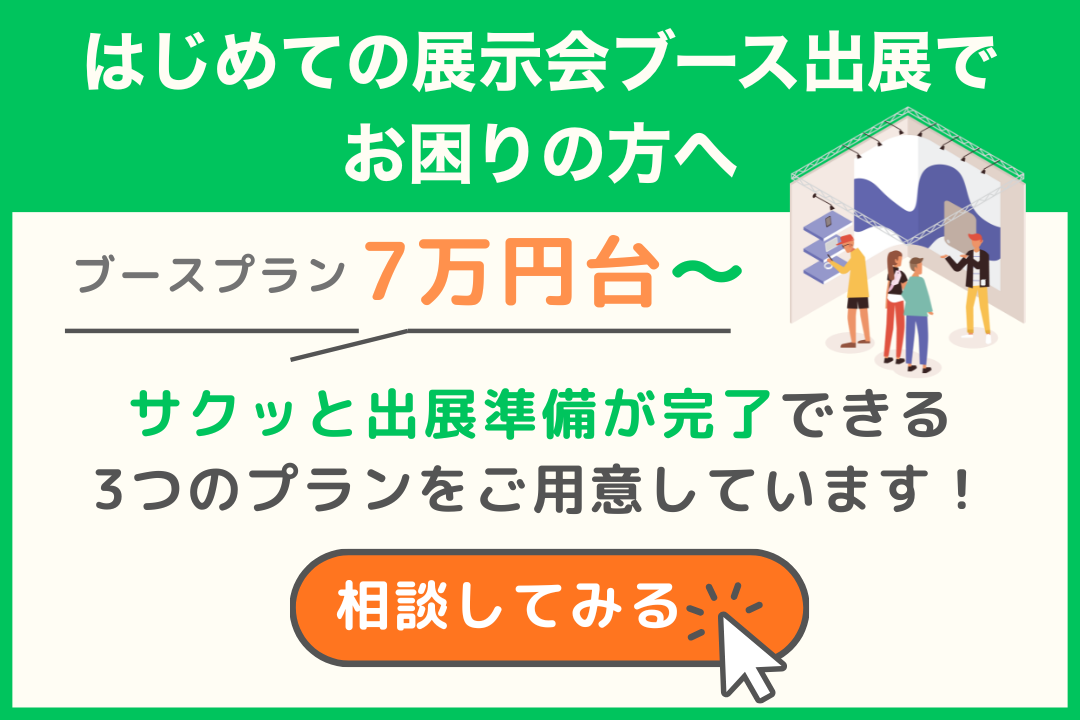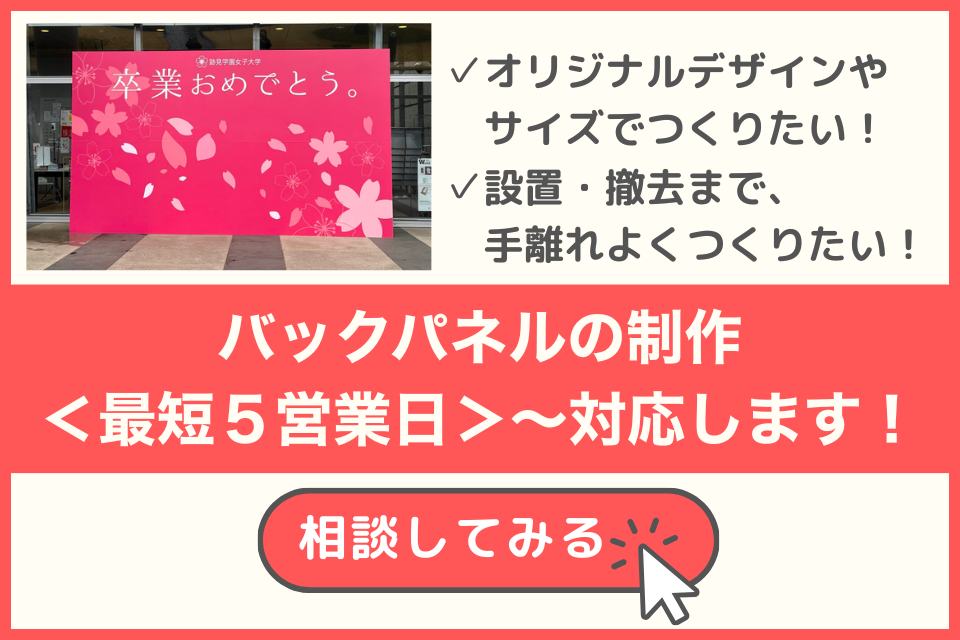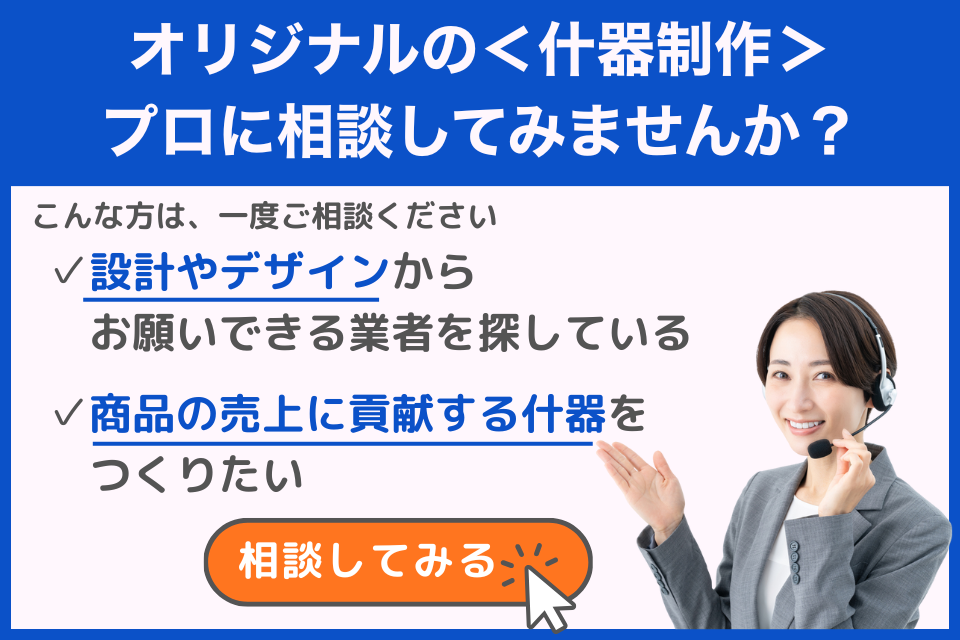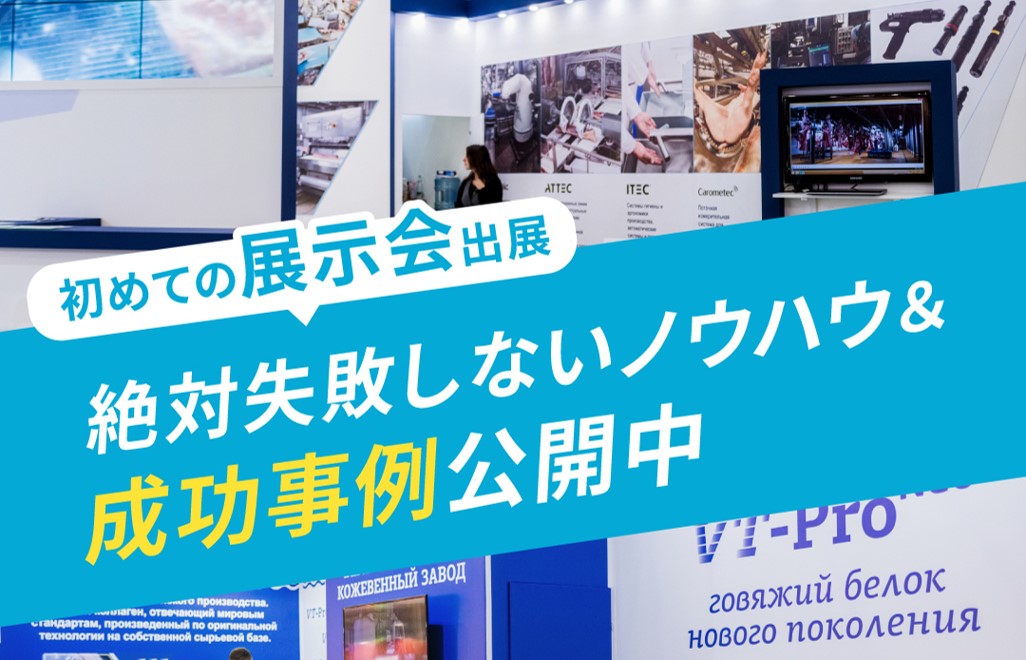- 展示会ノウハウ
展示会の備品リスト完全版|失敗しないための必須アイテムと準備のコツ
公開日 2025.10.31 /更新日 2025.11.06

名刺入れやアンケート用紙といった基本的なものから、プレゼンテーション用の機器まで、必要な備品は多岐にわたります。
しかし、「何をどれだけ準備すれば良いのかわからない」「当日になって足りないものが出てきたらどうしよう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、展示会に必要な備品を「全エリア共通」「エリア別」「あると便利なもの」に分けて詳しく紹介します。
さらに、初めて展示会に出展する方でも安心して準備を進められるようチェックリストの作り方も解説するので、参考にしてください。
もし「備品やブースの準備を相談したい」「自社に合わせた用意すべきものを知りたい」という方は、はじめての展示会へご相談ください。
貴社のサービスや目的に合わせて、専門家が準備すべきものをご提案いたします。
レンタル品の手配やブースの施工、撤収も承りますので、まずは以下のボタンからお気軽にご連絡ください。
Contents
備品の準備が展示会の成功を左右する理由

展示会を成功させるためには、備品の準備が重要です。
備品が不足していると、来場者対応の遅れや商談機会の損失など、さまざまなトラブルを引き起こします。
トラブルの例
|
このような小さな準備不足がスタッフの混乱を招き、企業のイメージの低下にもつながります。
こうした事態を防ぐために、スタッフ間で必要な備品をしっかり共有し、誰が何を担当するのかを明確にしておきましょう。
準備不足やミスを防げるだけでなく、時間やコストの削減にもつながります。
【全エリア共通】運営管理に必須の基本備品リスト7選

展示会の運営をスムーズに進めるためには、どのエリアでも共通して必要となる基本的な備品があります。
ここでは、運営管理に欠かせない基本備品を7つ紹介します。
【全エリア共通】運営管理に必須の基本備品リスト7選
|
これらをしっかりと準備することで、展示会当日の混乱を防ぎ、安定した運営が可能になります。
展示会運営マニュアル
展示会運営マニュアルとは、ブースでの対応手順や配布物の説明、よくある質問とその答え方などをまとめた手引きのことです。
展示会当日の対応を統一し、スタッフ全員が同じ品質で来場者対応をおこなうために欠かせません。
マニュアルに記載しておくべき主な項目は、以下のとおりです。
|
これらの情報をまとめておくことで、どのような状況にも落ち着いて対応できます。
スタッフのシフト表
展示会は長時間にわたることが多く、スタッフが交代で休憩を取りながら対応する必要があります。
そのため、スタッフのシフト表は、人員配置と休憩時間を明確にし、ブース運営に空白の時間を作らないために必須です。
シフト表を作成する際は、以下の内容を明確にしておきましょう。
|
また、シフト表はバックヤードに掲示するだけでなく、全スタッフのスマートフォンでも共有できるようにしておくと便利です。
リアルタイムで確認できる環境を整えておくことで、急な変更にも柔軟に対応できます。
適切なシフト管理ができているブースは、来場者からの印象も良く、結果的に商談の機会を増やすことにつながります。
配布物と管理表
展示会では、会社の紹介パンフレットやブースの説明資料、ノベルティグッズなどを来場者に配布します。
これらの配布物を忘れてしまったり、途中で足りなくなったりすると、せっかくの商談チャンスを逃してしまう可能性があります。
そのため、配布物の管理表を用意し、在庫の把握と補充タイミングの管理を徹底しましょう。
管理表には、以下の内容を記載して使用しましょう。
|
特に人気のある資料やノベルティは、予備を多めに準備しておくことが大切です。
展示会当日は来場者の流れが予測しにくいため、配布数を定期的に記録しておくことで、在庫切れを防げます。
おすすめのノベルティは以下の記事で紹介しておりますので、あわせて参考にしてください。
筆記用具
筆記用具は、使用頻度が高い備品のひとつです。
アンケートの記入や来場者情報のメモ、掲示物の修正など、あらゆる場面で使用します。
そのため、使用人数分に加えて3本以上の予備を準備しておくと安心です。
筆記用具が不足すると、アンケートの記入待ちが発生したり、スタッフ間のメモ伝達が滞ったりして業務が非効率になります。
細かい備品ほど忘れやすいため、チェックリストに含めておきましょう。小さな備えが、当日の運営をスムーズに進める助けになります。
メモ帳・付箋
メモ帳や付箋は、来場者との会話内容や商談中のポイント、スタッフ間での申し送り事項などを記録するために欠かせません。
展示会当日は多くの来場者が訪れるため、すべての会話を覚えきれませんし、口頭での情報共有だけでは抜け漏れが発生しやすくなります。
そのため、来場者の関心ポイントや質問内容をメモに残しておき、後の営業やフォローに活用しましょう。
紛失時や足りなくなった際に備えて、余裕をもった数を用意しておくと安心です。
名刺サイズカード(無地)
展示会では、来場者から名刺を受け取ることが一般的ですが、なかには名刺を持ってきていなかったり、名刺を切らしてしまったりする方もいらっしゃいます。
そのような場合に備えて、連絡先を記入してもらうための無地の名刺サイズカードを準備しておきましょう。
このカードに来場者の氏名や連絡先、所属などを記入してもらえば、会期終了後にお礼メールや資料送付をおこなう際の連絡先として活用できます。
カードには自社のロゴを印刷しておくと、ブランドの印象を残すことも可能です。小さな配慮かもしれませんが、展示会後のフォローアップにつながる重要な備品です。
アンケート
アンケートは、展示会の効果測定と顧客分析に欠かせません。
来場者にアンケートを配布し記入してもらうことで、ブースに訪れた方の客観的な感想や意見を把握できます。
またアンケート結果を分析すれば、次回の展示会に向けた改善点を発見できるだけでなく、見込み顧客が抱える具体的な課題やニーズも明らかになります。
これらは、今後の営業活動や商品開発に役立つ貴重な情報源です。
事前にどのような質問をするか、どのように回収するかを計画し、十分な枚数のアンケート用紙と筆記用具を用意しておきましょう。
また、アンケートの回収には施錠できるボックスを使用すると、情報漏洩を防げます。
【エリア別】ブース運営に欠かせない備品リスト

展示会のブースは、受付、商談、プレゼンテーション・デモなど、いくつかのエリアに分かれており、それぞれ役割に応じた特別な備品が必要になります。
ここでは、エリアごとに欠かせない備品を紹介します。
受付エリア
受付エリアは、来場者が最初に接する場所であり、第一印象を決める重要なエリアです。
必要な備品を万全にそろえることで、スムーズな受付対応と好印象の獲得ができます。
受付での対応の質が、その後の商談や企業イメージに直結するため、備品不足は待ち時間の増加や混乱を招き、来場者の離脱につながります。
受付エリアに必要な備品は次のとおりです。
|
これらをそろえておくことで、来場者を気持ちよく迎え入れられます。
商談エリア
商談エリアは、来場者とじっくりと話し合い、商品やサービスの契約、つまり成約につなげるための大切な場所です。
来場者がリラックスして話せる快適な環境と、商談を円滑に進めるために必要な備品を整えることで、商談の質を高め、成功率を向上させられます。
もし落ち着いて商談できる環境がなければ、来場者はすぐに立ち去ってしまい、大切な商談の機会を逃してしまうことになります。
商談エリアに必要な備品は次のとおりです。
|
プレゼンテーション・デモエリア
プレゼンテーション・デモエリアは、製品やサービスの魅力を最大限に来場者に伝えるための場所です。
ここでは、機器のトラブルを未然に防ぎ、効果的なプレゼンテーションやデモンストレーションを実現するための備品が必須です。
デモやプレゼンテーションが成功するかどうかが、その後の商談の成約率に直接影響します。
機器の不具合や準備不足があると、来場者の興味を失わせてしまう致命的なリスクにつながるため、細心の注意が必要です。
このエリアで準備すべき備品としては、以下のものが挙げられます。
|
なかでも、ケーブル類や予備バッテリーは忘れがちです。当日のトラブルを防ぐために、必ず準備しておきましょう。
その他展示会にあれば便利な備品類

その他にも、展示会にあると便利な備品があります。
|
これらの備品は必須ではありませんが、準備しておくことで当日のトラブル対応力が向上します。
テープ類や工具、延長コードなどは「忘れがちだが当日最も使う備品」です。
初めて展示会に出展する企業は、「トラブル防止用キット」としてまとめておくと安心です。
展示会の備品選びのコツ3選

展示会の備品を選ぶ際には、ただ必要なものをそろえるだけでなく、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
ここでは、展示会の備品選びの3つのコツを紹介します。
展示会の備品選びのコツ3選
|
1つずつ解説していきます。
1.設営の手間が少ない備品を選ぶ
展示会の備品選びのコツとして、設営の手間が少ない備品を選ぶことが挙げられます。
展示会の設営は、限られた時間のなかで多くの作業をこなす必要があるため、いかに効率よく進めるかが重要です。
組み立てが簡単なものや、工具を使わずに設置できるものを選ぶと、当日の作業がスムーズに進み、スタッフの負担も軽減します。
例えば「LANケーブル不要のWi-Fi対応プリンタ」「開くだけで設置完了する自立式看板」「ボタンで高さ調整可能な折りたたみテーブル」などが挙げられます。
2.運搬が簡単な備品を選ぶ
展示会の備品は、運搬が簡単な備品を選びましょう。
展示会会場への備品の搬入・搬出作業は、時間制限がある中で行われることが多いです。
そのため重いものや大きな備品は運ぶのに時間がかかり、スケジュールが遅れたり事故が起きたりするリスクが高まります。
折りたたみ式や軽量のものを選ぶことで、破損のリスクや運搬の負担を減らせます。
例えば、キャスター付きのケースや、軽量で分解・収納しやすい備品などです。
運搬のしやすさを意識して備品を選ぶことで、搬入・搬出時のストレスを減らし、展示会全体のスケジュールを滞りなく進められます。
3.ブースのコンセプトや企業イメージに合う備品を選ぶ
ブースのコンセプトや企業イメージに合った備品を選ぶことで、統一感のある空間を演出し、来場者に強い印象を残せます。
例えば、ファミリー層をターゲットにした企業であれば、明るいイエローやオレンジのトーンで統一された備品を選びましょう。
一方でバラバラな色やデザインの備品を使ってしまうと、ブース全体の統一感が崩れ、企業のブランドイメージが曖昧になってしまいます。
什器や装飾のデザインが決まっている場合は、それらに合わない備品は避けましょう。備品一つひとつが、来場者に与える印象を左右します。
とはいえ、初めて展示会に出展する場合は、どんな備品をそろえればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。そのような方は「はじめての展示会」へご相談ください。
はじめての展示会では、ブースのコンセプトに合わせた備品選びやレンタル品の手配など、複数のプランをご用意しています。
出展規模やご予算に応じた複数のプランをご用意していますので、以下のボタンからお気軽にご相談ください。
展示会備品チェックリストの作り方・使い方

展示会の準備を効率的に進め、備品の漏れをなくすためには、しっかりとしたチェックリストの作成と活用が欠かせません。
ここでは、効果的な展示会備品チェックリストの作り方と使い方を紹介します。
展示会備品チェックリストの作り方・使い方
|
順に解説していきます。
1.エリア別・用途別にカテゴリーを分ける
展示会ブースは、受付、プレゼン、バックヤードなど、複数のエリアで構成されており、それぞれ必要な備品が異なります。
そのため、一括で管理しようとすると、どうしても漏れが発生しやすいです。
備品をエリア別・用途別にカテゴリー分けすることで、準備漏れを防ぎ、効率的な管理ができます。
具体的なカテゴリーの例は次のとおりです。
|
このように細かく分類することで、必要な備品を1つずつ確実に確認できます。
2.数量・担当者・期限を明記する
チェックリストには、単に備品名だけを記載するのではなく、数量、担当者、そして準備期限を具体的に明記することが大切です。
指示が曖昧なままだと、準備漏れや重複発注が発生し、当日のトラブルにつながる可能性があります。
Excelやスプレッドシートを使ってチェックリストを作成し、複数人で進捗を共有すると、より効果的に管理できます。
記載すべき項目は、次のとおりです。
|
これらの情報を明記することで、準備の進み具合が一目でわかります。
3.当日の確認体制を整える
展示会当日の朝には、チェックリストを使った最終確認を実施し、備品の配置や動作確認をおこないましょう。
搬入時の紛失や破損、配置ミスを早期に見つけ、開場前に対処することが大切です。
例えば、プロジェクターが正しく映るか、マイクの音声がしっかり出るかなど、実際に使う状況を想定して1つひとつ確認しましょう。
当日の朝の確認を習慣にすることで、予期せぬトラブルを最小限に抑えられます。
展示会の備品準備でお悩みなら「はじめての展示会」におまかせ

展示会の備品準備は、リストアップから調達、搬入まで多くの手間と時間がかかります。
特に初めて展示会に出展する場合「自社の場合、何を準備すれば良いのかわからない」「当日何かトラブルがあったらどうしよう」といった不安を抱えることも多いのではないでしょうか。
そのような場合は「はじめての展示会」の無料相談をご利用ください。専門家が貴社の目的やご状況を伺い、準備すべき備品やトラブル防止に向けたアクションをご提案いたします。
レンタル品の手配やブースの施工、撤収も承りますので、お困りの方は下記のリンクからお気軽にご連絡ください。
展示会の成功は備品準備から

展示会の成功は、備品準備の段階で大きく左右されます。本記事で紹介したエリア別のチェックリストを活用し、計画的に準備を進めましょう。
準備が遅れてしまうと、それが不安につながり、展示会当日のスタッフのパフォーマンス低下を招くことにもなりかねません。
余裕を持って備品を整えることが、来場者への質の高い対応と、展示会全体の成功へとつながります。
もし備品準備に関してご不安な点があれば「はじめての展示会」が全面的にサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事に関するタグ







.jpeg)