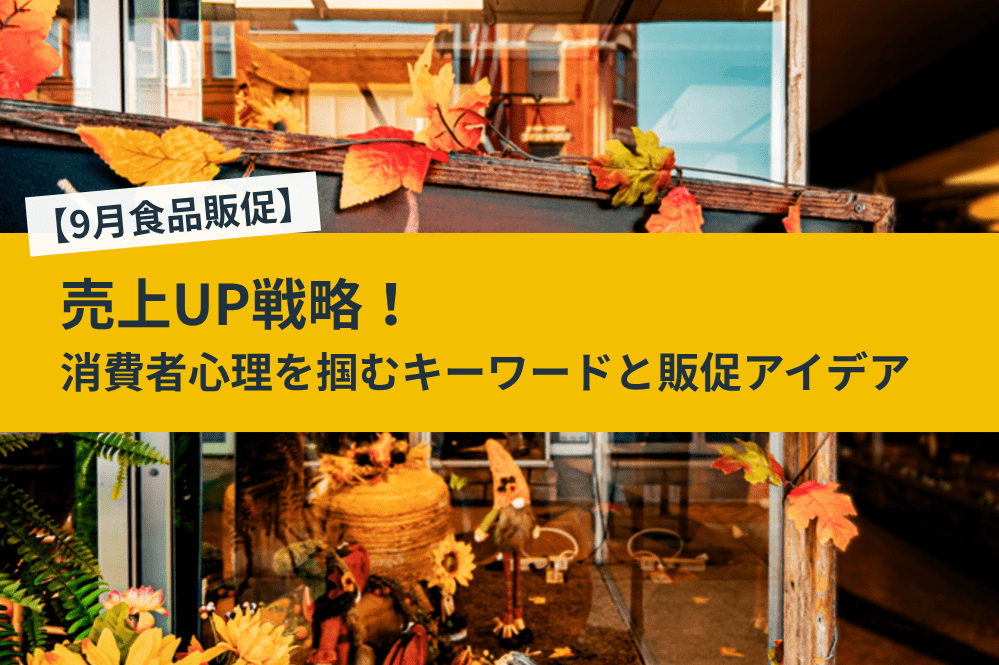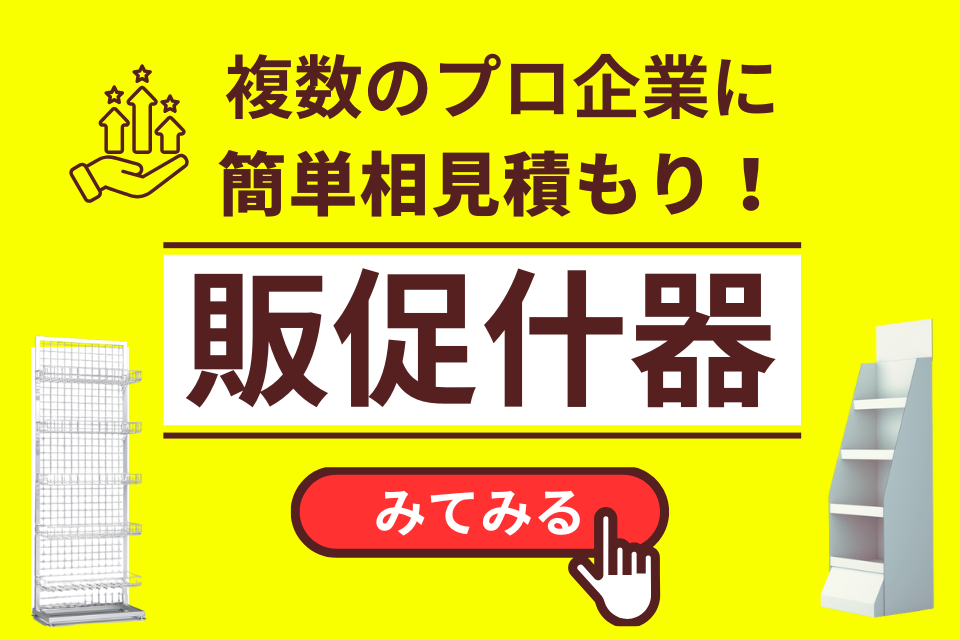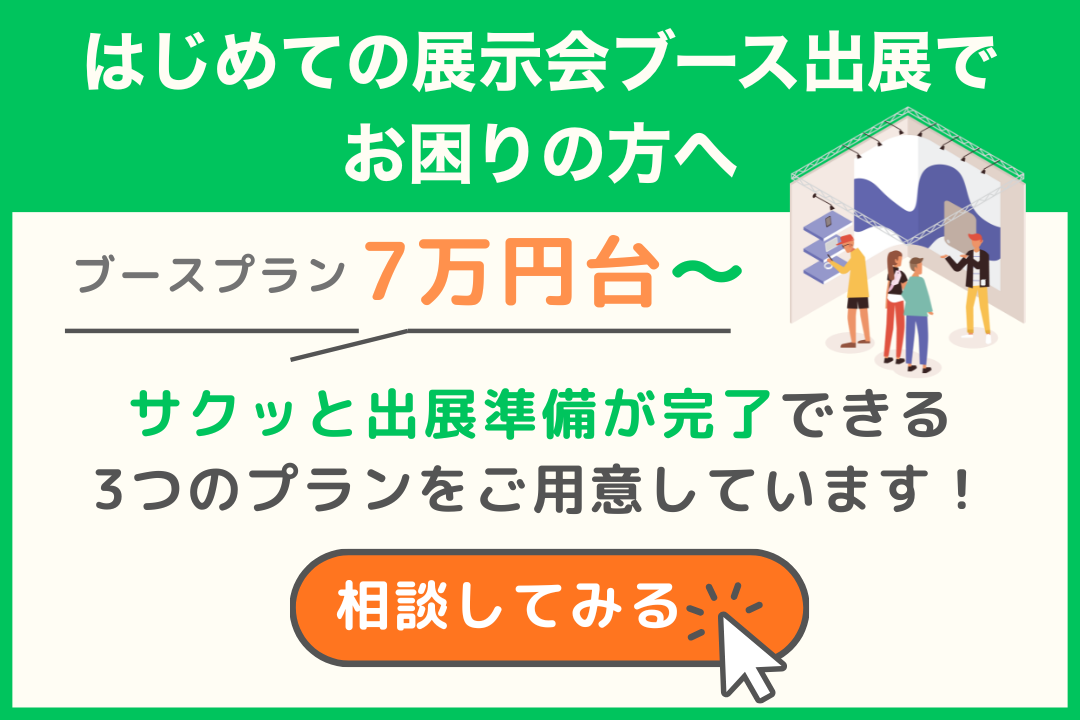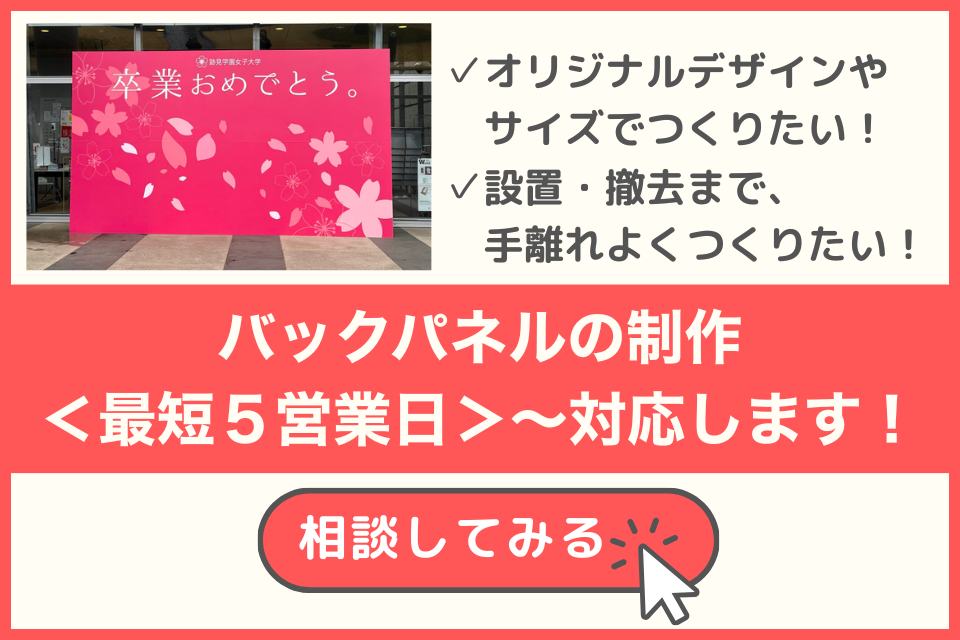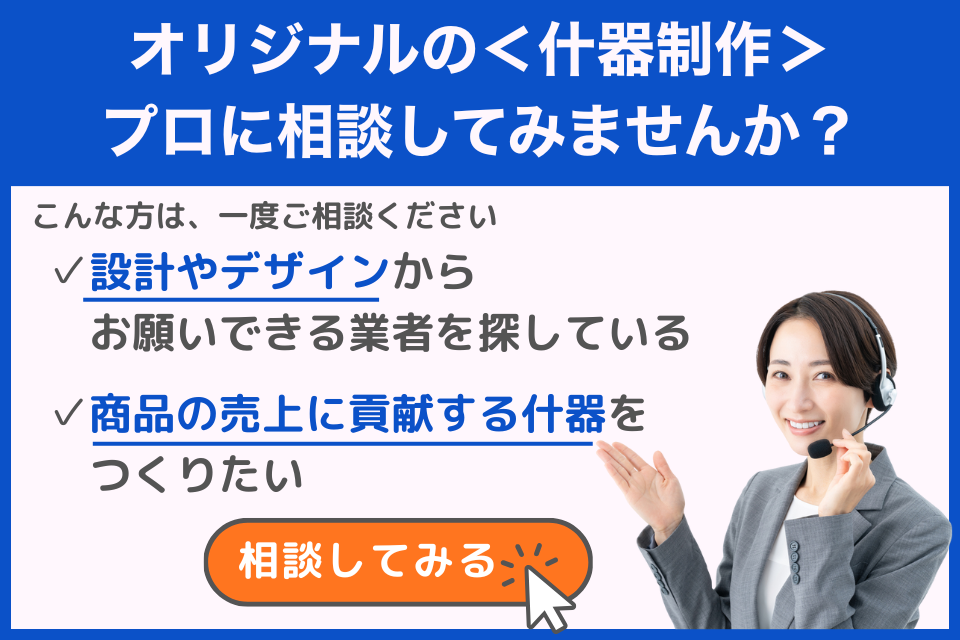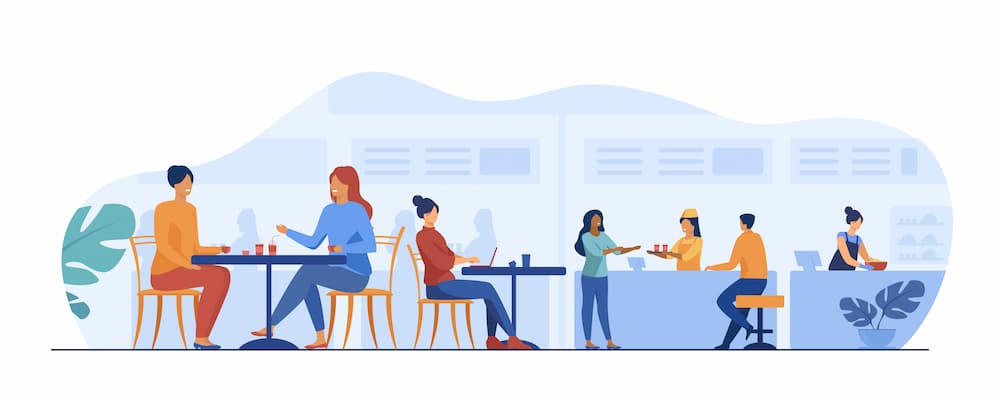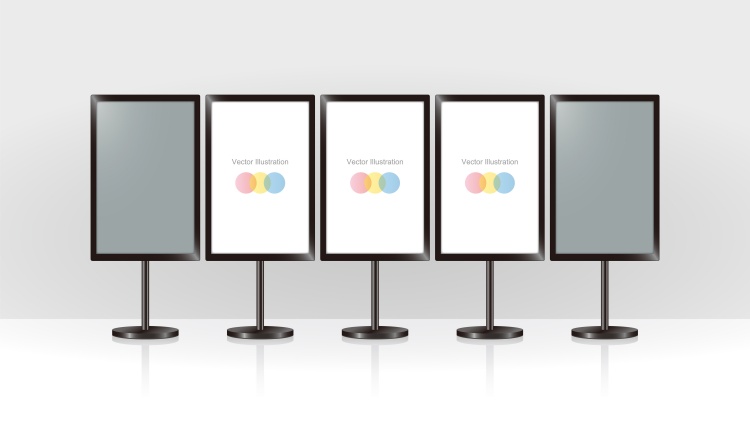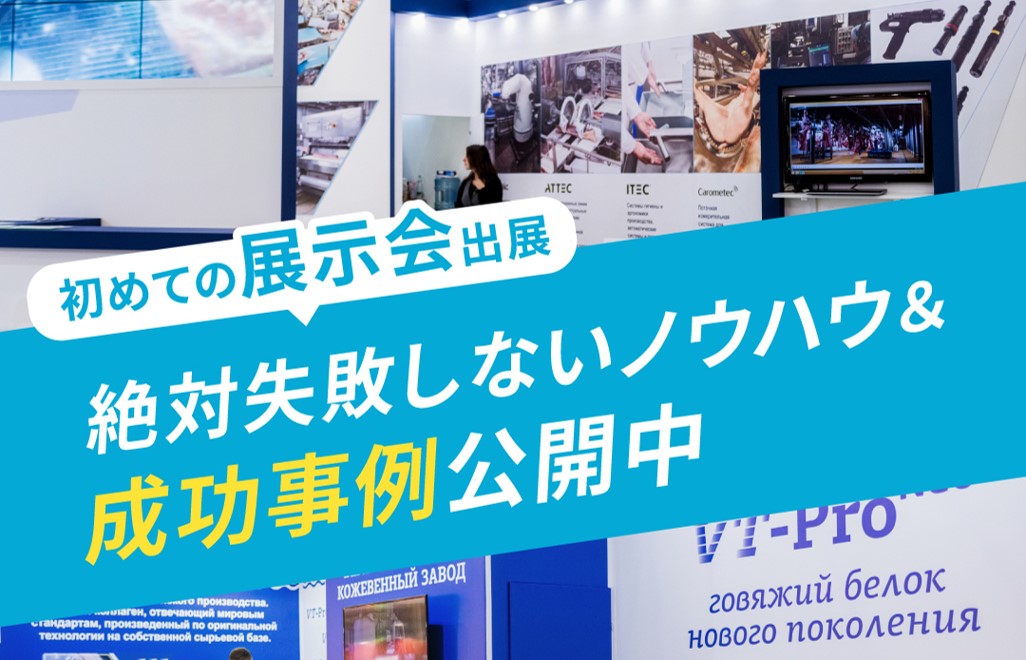- 展示会ノウハウ
展示会を視察する3つのポイントとは?報告書のフォーマットも紹介
公開日 2025.05.26 /更新日 2025.10.23

Contents
展示会を視察する主な3つの目的
展示会を視察する目的は主に以下の3つです。
展示会を視察する主な3つの目的
|
それぞれ解説します。
1.自社が出展する際の参考にする
展示会を視察する主な目的として、まず自社が出展する際の参考にすることが挙げられます。
競合他社はどのようなブースデザインを使用しているのか?どのような看板で商品をアピールしているのか?など、自社が出展する際に活かせます。
特に初めて出展する際には、ゼロからデザインや訴求方法を考えるよりも、モデルとなるブースを見つけると準備がスムーズです。
例えば、デジタルサイネージで商品紹介の動画をループ再生しているブースでは、来場者が立ち止まって映像を視聴し、滞在時間が長かったとします。
視察でこのような発見ができれば、自社が出展する際にも「新商品の紹介動画を制作する」といった戦略の立案が可能です。
視察して得られた知見は、自社が出展するときのアイデアにつながります。
2.市場の動向やトレンドを把握する
市場の動向やトレンドの把握も、展示会を視察する目的の1つです。
展示会には競合他社をはじめ、自社と同じ業界のさまざまな企業が出展しています。そのため、市場の動きやトレンドを把握でき、最近の商品の傾向や顧客のニーズをつかむことが可能です。
例えば、IT・テクノロジー業界向けの展示会で、「AI搭載」を訴求する企業が多く見受けられた場合、AIを活用したサービスへの注目度が高まっていると考えられます。
トレンドやニーズを把握できれば、自社サービスでもAIの搭載を検討したり、訴求を強めたりするなどの検討が可能です。
3.競合を分析する
競合の分析も、展示会を視察する目的です。
展示会を視察すると、競合他社がどのようなターゲット層を狙っているのか、どのような技術や強みを持っているのかを把握できます。
例えば、人事システムを開発する競合を視察した結果、以下が判明したとします。
- ・ターゲット:人事部長
- ・持っている技術:AIを導入して従業員の得意な業務を分析
上記をもとに、自社では別のターゲットを定めたり、競合にはない技術を訴求したりして、差別化するポイントを明確にすることが可能です。
展示会で競合を分析して、自社の商品をアピールするときの参考にしましょう。
展示会を視察する前の3つの準備
展示会を視察する前に準備しておきたいことが3つあります。
展示会を視察する前の3つの準備
|
順に見ていきましょう。
1.立ち寄るブースをピックアップする
展示会を視察する前に、立ち寄るブースを厳選するのも重要です。
小規模の展示会であればすべてのブースに立ち寄れる場合もありますが、通常はすべてのブースを回るのは時間的に困難です。
そのため、まずは展示会の公式サイトで出展企業のリストや会場マップを確認し、訪問する企業をピックアップしましょう。
なお、視察の目的に応じて企業を選ぶ基準が変わります。
- ・自社が出展する際の参考にする場合や、競合を分析する場合:同じような規模の企業や競合他社を選ぶ
- ・市場の動向やトレンドを把握したい場合:流行の技術などを取り入れている企業を選ぶ
ブースを選べたら「必ず訪問」「できれば訪問」「時間があれば訪問」のように優先順位をつけておくと、効率的に展示会を回れます。
2.当日のスケジュールを組んでおく
訪問予定のブースや参加したいセミナーを決めたら、どのような順序で回るのかスケジュールに落とし込むことを推奨します。
スケジュールを決めないと、成り行きに任せて動いてしまい、訪問する予定のブースに立ち寄れない恐れがあります。
そのような失敗を防ぐためにも、セミナーなど自分で動かせないスケジュールを軸にして、合間で訪問するブースの順番や時間配分を考えましょう。
なお、人気のセミナーは事前予約が必要な場合もあるため、早めに申し込みを済ませるのがおすすめです。
ただ、当日になって立ち寄りたいブースを変えたり追加したりする可能性もあります。
そのため、時間に余裕を持たせたスケジュールを立て、あくまで大まかな予定として考えておきましょう。
3.視察のチェックリストを作る
視察する際のチェックリストの作成も、視察前に済ませておきたい準備の1つです。
展示会の視察後は、社内で報告書の提出を求められる場合があります。
そのような場合に備えて、報告書に記載する項目に沿ってチェックリストを作成のうえ視察を進めると、報告書の作成がスムーズです。
報告書の項目が特に決まっていない場合は、まず報告書に含める内容を決定してからチェックリストを作成します。
報告書に何を書けば良いか迷う際は、後述するフォーマットを参考にするのがおすすめです。
なお、特に会社から報告書の提出を求められなくても、チェックリストを作成しておくと自社ブースを出展する際の参考にできます。
当日はチェックリストを確認しながら会場内を回り、視察で確認すべきポイントを見落とさないようにしましょう。
展示会を視察するときの3つのポイント
展示会の当日、実際に視察をするときのポイントは以下の3つです。
展示会を視察するときの3つのポイント
|
順に解説します。
1.会場全体を俯瞰してから回る
展示会を視察するときは、まず会場全体をざっと見て回り、展示会の全体像を把握するのがポイントです。
全体を俯瞰してから視察を始めると「後から視察したいブースが見つかったものの、時間がなくて回れなかった」といった失敗を防げます。
また、最初に会場全体を軽く一周すると、必ず見たいブースや新たに気になったブースの位置を確認でき、あらためて回り方を考える際の参考にできます。
限られた視察の時間を有効に使うためにも、最初に会場の全体像をつかみましょう。
2.積極的に質問してメモをとる
展示会の視察では、疑問に思った点をその場で質問し、積極的に担当者との名刺や情報の交換をおこなうことも重要です。
パンフレットに記載されていない詳しい情報や、価格についての相談が可能かなど、詳しい情報をすぐに確認できます。
例えば、「新商品の掃除ロボットの運転音が従来比でどれくらい静かなのか」がわからない場合、以下のように質問するとより詳細な情報を得られます。
- ・「稼働時の騒音レベルは測定値何dBで、従来比でどれくらいか」
- ・「どのような環境で騒音を測定したか」
質問内容と回答は以下のようにメモへ残し、後日作成する報告書に記載しましょう。
- ・稼働時の騒音:30dB(実験室で測定)
- ・従来比:–10dB
- ・所感:騒音対策が十分であり、病院や図書館などの静かな環境にも向いている
そのほかにも、同業他社のWebサイトには載っていない情報(料金やオプションサービスなど)も聞いておくことで、自社のサービス開発に活用できる可能性があります。
展示会は普段会えない企業の担当者と直接話せる機会でもあるため、積極的に質問するのがおすすめです。
3.セミナーやデモに参加する
展示会のブースで開催されるセミナーや製品のデモンストレーションにも、参加しましょう。
セミナーやデモンストレーションなどのイベントでは、短時間で業界のトレンドや製品の特徴といった要点を把握できるためです。
また、話し方や見せ方、内容の構成なども観察でき、自社が出展する際のセミナーやデモンストレーションに活かせます。
実際に参加して気付いた点や改善点があれば、「デモンストレーションで製品を実際に使うときは、ゆっくり操作しないとわかりにくい」のようにメモを残しましょう。
イベントに参加して気付いた点を自社が出展する際に反映させれば、来場者の満足度を高められます。
【フォーマット】展示会視察の報告書に載せる6つの項目
展示会を視察した後に作成する報告書は、以下のようなフォーマットで作成します。
フォーマットは以下からコピーできます。
記載する項目について、順に見ていきましょう。
1.展示会の概要
「展示会の概要」には、視察した展示会の概要を、報告書のタイトルを書くつもりで記載します。
概要を記載すると、報告書を読む人が展示会のおおよその内容を把握でき、報告書を読み進めやすいためです。
一例として、概要には以下を記載します。
- ・展示会名
- ・開催日時
- ・会場
冒頭に展示会の概要を載せて、内容を把握しやすい報告書を作成しましょう。
2.報告者・作成日
「報告者・作成日」では、報告書を作成した人物の氏名と、報告書の作成日を記載します。
報告者名を記載すると、誰の責任のもとで作成されたのかがわかり、報告書の内容について質問や確認が必要な際の連絡先を明確にできます。
また、作成日として記載するのは展示会の開催日ではなく、実際に報告書を作成した日付です。
展示会の当日に報告書を作成しているとは限らないため、報告書の作成日を記載すると、情報の鮮度を読み手に伝えられます。
3.視察の目的
「視察の目的」では、以下のように展示会を視察した目的を示します。
- ・自社が出展する際の参考にするため
- ・市場の動向やトレンドを把握するため
- ・競合を分析するため
目的を書くと、報告書を読む人は「どのような観点で視察がおこなわれたか」や「どのような内容の報告書なのか」といった大枠がつかめます。
目的を記載して、読み進めやすい報告書にしましょう。
4.視察内容
「視察内容」には、以下のとおり展示会で実際に視察できた客観的な事実のみを記載します。
- ・視察した出展ブース
- ・注目した製品の仕様や価格
- ・来場者数やブースの混雑状況
視察内容と次の項目で記載する「所感・分析」を分けると、読み手は客観的な事実と主観的な意見を区別して読み進められます。
また、「視察内容」の事実を踏まえると、「所感・分析」の内容に説得力を持たせることが可能です。
5.所感・分析
「所感・分析」では、気付いた点や感じたこと、自分なりに分析した点など、主観的な内容を書きます。
視察内容を踏まえ「次に自社ではどのようなアクションへつなげるべきか」を考えるきっかけになるためです。
実際に展示会へ足を運んだからこそわかる、会場の雰囲気や競合他社のブースの演出などを以下のように詳しく記載しましょう。
- ・「A社のブースが近未来をイメージさせる洗練されたデザインに仕上がっており、自社も視覚的なインパクトを強化する必要性を感じた」
- ・「来場者の年齢層が若く、デジタル技術への関心が高いため、次回の出展ではVR体験コーナーの設置を検討したい」
分析をもとに、自社が出展するときの方向性を具体的に提案すると、視察した内容を自社の展示へ活かせます。
6.添付資料
「添付資料」の欄では、資料を載せて報告書の内容を補完します。
資料を添付すると、文章だけでは伝えきれない展示会の具体的な様子や臨場感を読み手に伝えられるためです。
添付資料の例としては、以下があります。
- ・ブースの写真
- ・各社から配布された商品のカタログやパンフレット
- ・視察した商品の詳しい情報が掲載されているURL
文字だけですべてを伝えようとせず、資料を使ってわかりやすい報告書を作成しましょう。
視察した内容を活かして出展するなら「はじめての展示会」
「展示会を視察したものの、実際どのように出展準備を進めればいいかわからない」という場合は、展示会パッケージ「はじめての展示会」がおすすめです。
展示会への出展が初めてでも、予算や出展するブースの広さに合わせて、3つのプランからパックを選ぶだけで、準備がすぐに終わります。
各パッケージには出展に必要なアイテムが含まれているため、個別に手配する手間がかかりません。
また、「視察した企業のようなブースを作りたい」といった要望がある場合も、展示会ブースのプロへ無料で相談できるので、まずは以下より気軽にお問い合わせください。
展示会を視察して自社の出展を成功させよう
展示会を視察して他社のブースをチェックすると、自社の出展に活かせるほか、トレンドの把握や競合分析ができます。
視察前に準備をしたうえで、当日はスタッフへ質問したりセミナーなどのイベントに参加したりして、意義のある視察にしましょう。
もし、他社のブース運営や集客方法を活かすなら、展示会出展サービス「展示会マスター」がおすすめです。
ブースづくりから集客までをサポートしているので、視察で訪れた展示会のようなブースやチラシを作りたい場合に、各企業に合った提案ができます。
スタッフの手配もおこなっているため、視察したブースのようにスタッフの人員を増やしたい場合も、以下より無料でお問い合わせください。
この記事に関するタグ